令和元年10月13日に実施された一級建築士試験「設計製図の試験」における記述部分「計画の要点等」について説明します。
設計課題は「美術館の分館」です。「分館」は、美術、工芸等の普及活動拠点として、市民の創作、展示等を支援します。
今年度は、計画の要点等の設問として10問出題されました。
例年からの変更点
10問のうち、3問で補足図を記入する欄が設けられています。今までは、補足図(補足してもよい)は任意であったため、文章のみで設問に答えきることができていれば減点はありませんでした。
しかし、今年は「必ず記入のこと」と答案用紙Ⅱの問題文に書かれていたため、未記入の場合は「図面未完成」と判断され、即ランクⅣとなる可能性が濃厚となります。
出題内容
| 設問 | 内容 | 分野 |
| 1 | 「展示」と「アトリエ」のゾーニング | 計画 |
| 2 | 展示物移動に配慮した動線 | 計画 |
| 3 | 分館と本館の来場者動線 | 計画 |
| 4 | 展示室A、Bの室の設え | 計画 |
| 5 | 吹き抜け空間の平面・断面計画、開口部 | 環境 |
| 6 | 眺望、採光に配慮した日射負荷抑制(補足図) | 環境 |
| 7 | 屋上庭園の断面計画(補足図) | 構造 |
| 8 | 建築物の構造、架構、スパン、部材寸法 | 構造 |
| 9 | 多目的展示室の構造計画、部材寸法 | 構造 |
| 10 | 多目的展示室の空調吹出し口(補足図) | 設備 |
(1)「展示」と「アトリエ」のゾーニング
設計条件に、「分館」は市民の創作活動の支援、体験学習講座や創作活動で製作した作品等の展示、企画展等に使用するとあります。
このため、「展示」は市民が製作した作品展示を、「アトリエ」では市民の創作活動支援をすることと目的が異なることから、明確に分離するゾーニングが必要となります。
(2)展示物移動に配慮した動線
展示物の移動に関しては、人荷用EVの要求があったことから、大型の展示物を移動することを考慮しなくてはなりません。このため、展示物の動線である「廊下」、「出入り口」、は、十分な幅員を確保し、また「天井高さ」にも配慮することが求められます。
(3)分館と本館の来場者動線
平成30年「スポーツ施設」に続き、隣接施設との動線が問われました。
今回は、本館と分館の隣接部分が別図で記載され、本館の出入り口の位置を考慮する必要がありました。また、分館カフェに本館からのアプローチ指定がありましたので、こちらに関する記述も必要でしょう。
(4)展示室A、Bの室の設え
今年度はコンセプトルームの出題がありませんでしたが、室の設えを問う問題として出題されました。
なお、平成29・30年度では「設え(しつらえ)」の注釈がありました。以前と同様、内装(インテリア)、什器、設備等と考えればよいでしょう。
展示室Aは「光やその陰影に配慮」のため、遮光カーテンの設置や、展示に合わせた照明配置を考慮します。
展示室Bは「映像、音響等に配慮」のため、映像、音響装置の配置、スクリーン、遮光カーテン、防音のための壁や出入り口等について配慮します。
(5) 吹き抜け空間の平面・断面計画、開口部
近年ほぼ毎年出題されている、自然採光に関する問題です。吹抜けは、「整形の三層」が要求されました。吹抜けの平面的配置により場合分けが発生します。
外壁面に沿って吹抜けを配置
三層の窓から多くの自然光を取り入れ、各階共用部に届けます。
建物中央部に吹抜けを配置
トップライトから多くの自然光を取り入れ、各階共用部に届けます。
(6)眺望、採光に配慮した日射負荷抑制(補足図)
日射負荷抑制の方法を問われました。条件として、西、南面の公園眺望と自然採光の確保を要求されています。留意事項に「日射負荷抑制が必要な室のガラスはLow-Eガラスを使用」との条件があり、これ以外の工夫を示すことが求められています。
手法としては、庇、可動ルーバー、窓面の高さ等を用いた日射遮蔽手法を記述します。
(7)屋上庭園の断面計画(補足図)
屋上庭園の断面構造について問われました。以下のポイントについて記述します。
- 梁断面形状…客土部分と通路部分の段差を、適切に支持できる梁せい
- スラブ厚さ、梁との接続位置…客土深さ、重量を考慮したスラブ厚さ、接続位置
- バリアフリー…出入口の段差処理
- 防水…庭園部分を室内より200mm程度下げること、防水層を設けること
(8)建築物の構造、架構、スパン、部材寸法
毎年、必ず出題される項目です。ここでは、定型文を覚えておいて書き込むことで時間短縮します。
ただし、自分のプランに合致していることを十分確認しなくてななりません。
(9)多目的展示室の構造計画、部材寸法
多目的展示室は無柱空間の指定がありましたので、PC梁を用いた架構計画について記述します。ポイントは以下のとおりです。
- 柱…PC梁を支える柱を通常の柱よりもサイズアップ
- 梁…PC梁を用い、たわみやひび割れを抑制
- 天井…200㎡を超える大空間であることから特定天井とする
- スパン…短辺方向にPC梁を架け、架構の安定性に配慮
(10)多目的展示室の空調吹出し口(補足図)
多目的展示室は天井の高い大空間であることから、均一な気流分布と温湿度分布を保つために、吹出し口について考慮したことを記述します。
空調の吹出し口に関する問題は過去にも出題されていますが、今年度は吹出し口の設置位置を、床・壁・天井・幅木から一つ以上選択して記述するよう指示がありました。
まとめ
今年度の「計画の要点等」は、量が多く、難易度もかなり高かったと言えます。これまでとは少し違った切り口で、一瞬考えさせられる設問があったため、普段より記述に時間を取られた受験生が多かったと思われます。
日射負荷抑制についての設問では、西面の眺望と両立する必要があったため、多くの受験生が悩まされたでしょう。また、庭園の構造計画の設問は、かなり突っ込んだ内容であったため、梁やスラブの構造に関する理解が試されました。
しかし、自分が難しいと感じる問題は、まわりの受験生も同じように難しいと感じています。これらの問題に対して、あまり時間を使い過ぎずに割り切ることも重要です。


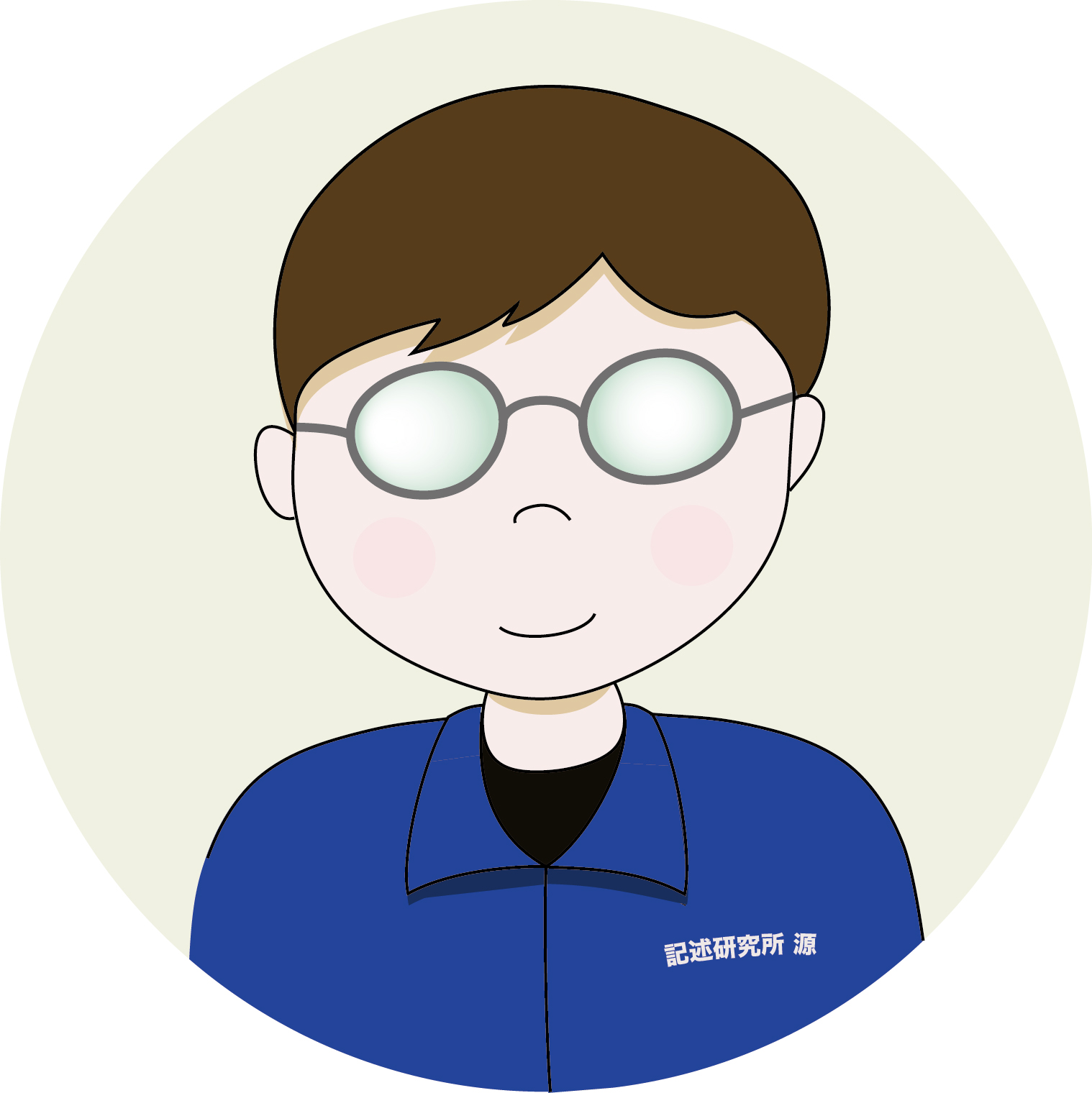





コメント